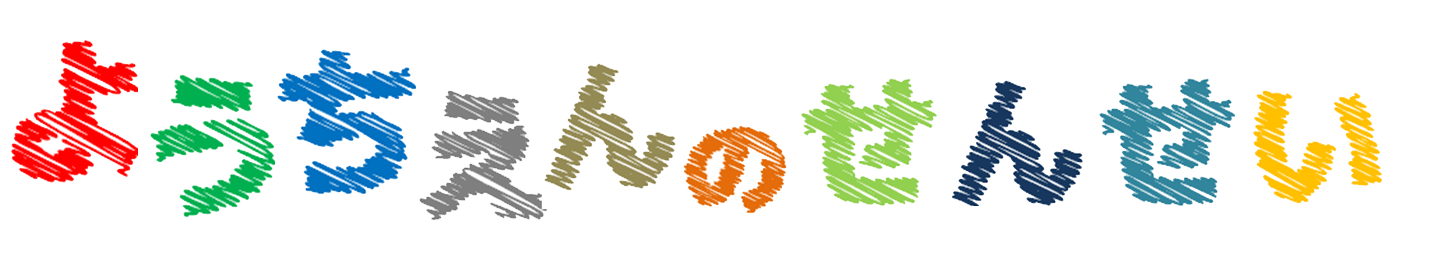自分はできる!有能感。幼児期に得たい自尊感情の育て方。
子どもは有能感を持っている
1番にこだわる子は多いですよね。子どもは本当に1番が大好きです。
まだまだ周り(他者)が見えない2~3歳の子は自分は万能で最強だと思っています。
少しづつ他者を意識するようになると自分のできないことを友だちができているのを見て焦ったり自信を無くしたりします。
そんな時に支えになるのが「1番」という言葉です。
早く支度を終えて「1番!」「今ズルした!」「してないよ!」と小さなことで競い合ってケンカになることもしばしばですね。
手軽な「1番」になることで失いかけた自己有能感を保っているのです。
理想の自分と現実の自分
「自分はもっとできる」と思っていた理想の自分と、思うようにできなかった「現実の自分」を知るようになり子どもは葛藤します。
すぐにかんしゃくを起こしたり、イライラしていたり、ちょっとしたことで泣いたり不安定な様子を見せることもあります。
保護者の方からも「この頃ちょっと不安定で・・・」なんて相談を受けることもありますね。
その子が葛藤の最中にいるのであれば時期が来れば収まります。ゆったり構えて見守ってあげてほしいなと思います。
なぜなら理想の自分があってそこに近づきたいと頑張っている証拠なのです。
そして保護者や保育者の「頑張っているね」「きっとできるよ」といった励ましが子どもの支えとなり意欲を高めます。
その結果、子どもは自分の力でやり遂げ「自分はやればできる」といった有能感が育ち「自分はすばらしい」と思えるようになります。
これが自尊感情です。
自尊感情が高いと・・・
もしも子どもがつまづいているときに「あの子は上手なのにあなたは駄目ね」などと言ってしまったら子どもの自尊感情は傷つき育ちません。
自尊感情が低いまま大人になると犯罪に簡単に染まりやすいと言われています。
逆に自尊感情が高いとどんな逆境や誘惑にも負けることなく「自分はそんな低い人間ではない」と誇りを持って生きることができます。
周りの大人のかかわり方ひとつで子どもが自分をどうとらえていくかが決まります。
みんなでかけっこをした時に1番になった男の子に「○○君は足が速いね」と言ったことがありました。
私にとっては何気なく褒めた一言でその男の子は「自分は足が速いんだ」と自信をもってサッカークラブに入りました。
その後も男の子は入院をしたりと挫折をしたもののずっとサッカーを続けていたそうです。
「あの時の先生の一言で・・・」と男の子のお母さんに教えていただきました。
よくある話かもしれませんが私はそれ以来、自分の発言が子どもの自己に大きく関わっていることを痛感しました。
たまたま良い話だから良かったものの、もしかしたらその逆も気が付かずにしてしまったかもしれません。
「この言葉で良かったかな」「傷つけていないかな」なんて今でも反省しながらこの仕事の責務を果たしていこうと思っています。
読んでいただきありがとうございました。