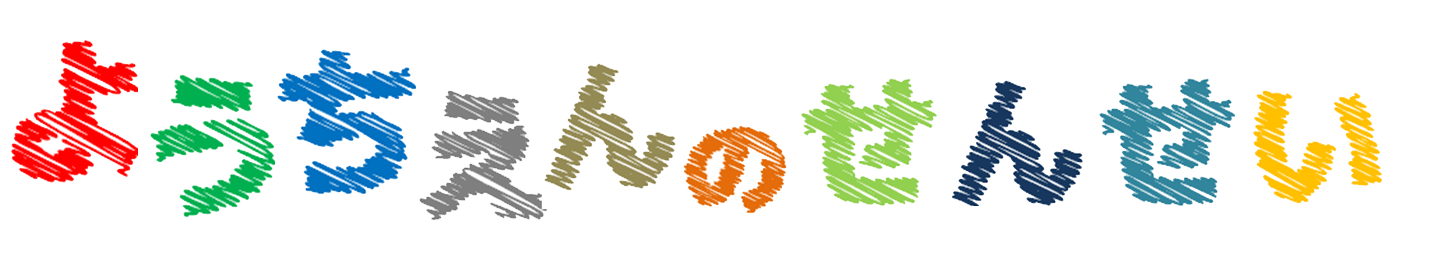間違った伝え方してませんか?マナーとルールを守れる子になるには・・・?子どもに伝えたいマナーとルールのお話。
利己的な道徳性
人は他人の行為の善悪などを判断する時に自分の中にある判断基準を用います。
その基準は「道徳性」と呼ばれます。
この道徳性は周りの大人のかかわりや、友だちとのかかわりの中で発達していきます。
乳幼児期は「お母さんがダメって言ってたから」など大人の規範が絶対で「他律」の時期です。
この時期は「怒られるから」という理由で善悪の判断をします。
そのため善悪の判断は利己的になります。
誰も見ていなければ禁止されていることをしてしまうこともあります。
また、お友だちとケンカをして相手が泣いてしまっても「だって先に嫌なことしたから」と正当化しようとします。
このように、まだまだ「怒られたくない」気持ちが優先ですが、集団の中で過ごすことで変化していきます。
社会的な道徳性
幼稚園などの集団生活に入って数ヶ月で自分の基準から社会的な基準へと変化します。
友だちの考えや目の当たりにした体験をもとに考えも発達していきます。
「みんながやっているから」とか「みんなに嫌われちゃう」など善悪の判断が先生や友だちからの評価になります。
今までは「怒られたくないからやる」だったのが「友だちに受け入れてもらいたい」と思うようになるためです。
入園したての子が「10回漕いだら交代」ルールのブランコに乗っていました。
みんなに「交代だよ」と言われても、なかなかブランコから降りません。
ルールを守るよりも自分の「ブランコに乗りたい」気持ちの方がはるかに上回っているからです。
でもしばらく経って仲の良い友だちが出来る頃には「10回で交代」を当たり前のように守っているのです。
ルールを守らないことで友だちに避難されることが嫌だからです。
このように集団の中で利己的な道徳性が社会的な道徳性へとなるのです。
人が作り出すのがルール
集団ができるとそこにはルールが生まれます。
大人数で絵本や紙芝居を観ている時には「前の人は座る」「お話ししない」などのルールが生まれます。
「立っている人がいたら後ろの人が見えないんだよ」「お話ししていたら聞こえないよ」と子ども同士理由を添えて注意しています。
これは快適に絵本や紙芝居を楽しむために子どもたちから生まれたルールです。
「人に言われてやる」ことから「自分たちのためにルールを考える」ことができるようになったということです。
これは子どもが「他律」から「自律」に変わったことを表します。
やがてお友だちと集団で過ごすために「みんなが快適に過ごす」ためにどうしたら良いのかを考えることができるようになります。
ルールとマナーは似て異なる?
「快適に過ごしたい」「気持ちよく過ごすために」必要なルールは「マナー」の部類に入ります。
守らなくても罰せられないけれど品格を問われるのがマナーです。
マナーは他人を思いやる「愛他行動」にも通じる行動であり子どもに身に付けてほしい思いやり行動です。
愛他行動は人に言われたからやる「他律」ではなく人のためにやってあげたい気持ちからくる「自律」であることが前提です。
これは周りの大人の行動と言葉による促しで身に付きます。
例えばレストランの中騒いでいる子どもを注意するのに「お店の人に怒られちゃうよ」と注意するのは「他律的」な促しです。
これでは子どもの道徳性も正しく育ちません。
「静かにご飯食べたい人もいるから静かにしようね」と言えば子どもはどうしたらみんなが快適に過ごせるか考えることができます。
自分で考えて決めるので「自律的」であると言えます。
「ルール」は集団で過ごすために「決められた」約束、「マナー」はお互いが気持ちよく過ごすために「決める」約束です。
マナーを不要だと思う人が多数派の社会よりマナーを大切だと思える人が多数派の社会が良いのは当然です。
子どもたちひとり一人がマナーのある道徳性を身に付けてほしいですね。
読んでいただきありがとうございました。